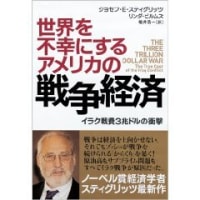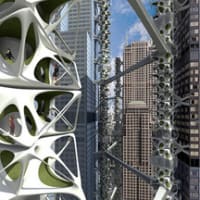This work is dedicated to the Public Domain
短編の名手として名高いサキの作品をのせておきます。個人的には、O・ヘンリーより好きですね。短いので気晴らしにどうぞ。これにはライセンスもはっておきます、というかパブリックドメインだけど。
開いた窓 サキ
「おばは今参っちゃってるの、ナッテルさん」とても落ち着いた声で15才の少女がそう言った。「だからわたしが相手するので我慢してくれなきゃだめよ」
フラムトン・ナッテルは、会うはずだったおばを無視しすぎないように、しかもその姪をちゃんとほめるような的確な一言を口にしようとしていた。ただ内心では、このまったくの他人を何人も儀礼的に訪問することが、神経を休めることに効果があるのかどうか、まぁそのためにやってたわけだが、いつも以上に疑っていた。
「私には成り行きがわかるわ」ナッテルがこの田舎の療養所に移住しようとしたときに妹は言った。「あなたはそこに自分をうずもれさせて、生きてる魂に話しかけるつもりはないのよ。ひきこもって、精神状態もわるくなっていくわ。そこで知っている限り全員の紹介状をあなたに書くわ。そのうちの何人かは、覚えてる限りではすごくいい人だったから」
紹介状をもらった女性、サップルトン夫人がいい人の部類にはいるのかどうかフラムトンはわからなかった。
「このあたりの人は、ほとんど知り合いですか?」姪は、無言での交流は十分と判断してそう尋ねた
「ほとんどだれも知りません。私の妹がここの牧師館に滞在したことがあって、そう4年ほども前になりますか、そして私にここにいる何人かの紹介状をくれたわけです」フラムトンは、発言の最後には少し後悔の念をただよわせ、そう答えた。
「じゃあ私のおばについては、全く何もしらないわけね」落ち着いた少女はそう続けた。
「名前と住んでいるところだけです」その訪問者は、サップルトン夫人が結婚しているか、未亡人なのか戸惑いながら、そう認めた。なんともいえない部屋の感じからは、どことなく男性が住んでる感じがしたが。
「おばの悲劇はちょうど3年前に起こったの」その子供は続けた。「あなたの妹さんがいた後ってことね」
「悲劇?」フラムトンは、この静穏な田舎に悲劇とはまた場違いな、と思いながらそうたずねた。
「10月の夕方にしては、窓を大きく開けてると思いません?」姪は、庭に向かって開いている大きなフランス風の窓を指差した。
「この時期にしては暖かいですからね」フラムトンは答えた。「あの窓が悲劇となにか関係あるんですか?」
「ちょうど三年前の今日のことです。あの窓から、おばの主人と二人の弟たちは狩猟で出かけていったんです。ところが帰ってきませんでした。自分たちの好みの狩猟場に行こうと、原野を横切っているときに、三人とも不安定な沼地に囲まれてしまったのです。そう、ひどく雨の多い夏でしたから例年なら大丈夫な場所でも、とつぜんなんの前触れもなしに沈み込んでいきました。死体も見つかりません。痛ましい話です」子供の声からはおちついた感じがなくなって、とつとつとした話ぶりだった。「おばはかわいそうに、いつか三人と、いっしょにいなくなった小さな茶色の犬が帰ってきて、いつもそうしていたように、あの窓から入ってくると思ってるんです。だからすっかり暗くなるまで、あの窓は夕方はいつもあけっぱなしになっています。かわいそうなおば。よくどうやって家からでていったかを話してくれました。叔父は白のレインコートをうでにかけていたと。ロニーは末の弟ですが、『バーティ、なぜ飛び跳ねてるの?』なんて歌いながら、彼女がそうされると気に触ると言っていたので、いつもそうやって彼女をからかっていたのです。今日みたいな静かな落ち着いた夕暮れには、窓からみんなが歩いて入ってきそうな気がしてぞっとします、わかります?」
姪が少し身震いして話をとめたので、おばが遅れたことを謝ろうと大騒ぎをしながら部屋にはいってきた時、フラムトンはほっとした。
「ベラがちゃんと楽しませてくれてたといいんだけど」とおばが言ったので、
「とても興味深かったですよ」フラムトンは答えた。
「窓が開いてるのは気になさらないでください」サップルトン夫人は手短にいった。「わたくしの主人と兄弟が狩りから帰ってきて、直接そこから入ってきますので。今日は沼地のほうに狩りにいってるから、わたくしのカーペットはざんざんなことになりそうだわ。あなたがた男ってそうよね?」
彼女は、狩りや鳥が少ないこと、この冬のカモの見込みについて楽しそうにおしゃべりした。フラムトンにとっては、ただただ恐ろしかった。必死に努力してなんとか、話を幽霊とは関係ないことにもっていくことにも少しは成功した。ただ彼女が気もそぞろで、その目はたえず自分の後ろの開いた窓、その向こうの庭に向けられていることにも気づいていた。まさしくこの悲劇の日に訪問してしまったことは、不幸な偶然の一致としかいいようがなかった。
「医者たちは口をそろえて、私が完全な休養を取るようにと、精神的に興奮しちゃだめだと、激しい運動のようなことも避けてくださいといいました」フラムトンはそう知らせると、どうしようもないほど誤解がひろがって、全く知らない人や偶然知り合った人が自分の病気や症状、原因や治療法についてどんなことでも聞きたがるとこぼした。「食事についても、医者たちはあまり意見が一致していないくらいですから」
「そうなの?」サップルトン夫人は最後にはあくびをかみころしたような声で答えた。それから急にはっとして注意をむけた、とはいってもフラムトンの言っていることにではなかった。
「とうとう帰ってきた」彼女は叫んだ。「ちょうどお茶の時間だわ、かれらったら全身泥だらけみたいね?」
フラムトンはかすかにふるえて、姪のほうを分かってくれるよなという風に見た。少女は目に恐怖の色をうかべ、開いた窓から外を見つめていた。なんともいえないぞっとする恐怖のショックで、フラムトンは座ったまま振り返って、同じ方向を見た。
夕闇が濃くなる中に、3つの姿が庭を窓の方に向かって歩いてきている。全員両脇に銃をもち、その上一人は両肩に白いコートをはおっていた。疲れ果てた茶色の犬が彼らの後に続いていた。音も立てずに家に近づき、それから夕暮れに若い男のしゃがれ声が響きわたった「言ったろ、バーティ、なぜ飛び跳ねてるの?」
フラムトンは手当たりしだいにステッキとぼうしをひっつかむと、玄関、砂利道、門のどこがどこだかわからないくらい大急ぎで逃げ出した。そこに一台の自転車が道をやってきたが、出会いがしらにぶつかるのを避けるため生垣につっこむありさまだった。
「かえってきたよ、おまえ」白いレインコートをかかえた男は、窓から入ってきながらそういった。「かなりどろだらけになったけど、ほとんどは乾いたな。帰ってきたときに誰かが飛び出してったみたいだが?」
「ナッテルっていうのは本当にむちゃくちゃな人ね」サップルトン夫人は答えた。「自分の病気のことだけを話したかと思えば、あなたがたが帰ってきたら、一言のさよならも断りもなく走っていなくなったの。幽霊でもみたのかと思うわ」
「犬だと思う」姪は落ち着いて言った。「犬が怖いんだって言ってたもの。ガンジスの土手かどこかの墓地でバリア犬の一群に追いかけられたって。そして新しく掘った墓穴で、自分の上を犬たちがうなり声をあげたり、歯をむき出したり、口から泡をふいたりする中で一晩をすごしたんだって。神経をやられるのも無理ないわ」
とつぜんに荒唐無稽な話をでっちあげるのが、姪の得意技だった。
「おばは今参っちゃってるの、ナッテルさん」とても落ち着いた声で15才の少女がそう言った。「だからわたしが相手するので我慢してくれなきゃだめよ」
フラムトン・ナッテルは、会うはずだったおばを無視しすぎないように、しかもその姪をちゃんとほめるような的確な一言を口にしようとしていた。ただ内心では、このまったくの他人を何人も儀礼的に訪問することが、神経を休めることに効果があるのかどうか、まぁそのためにやってたわけだが、いつも以上に疑っていた。
「私には成り行きがわかるわ」ナッテルがこの田舎の療養所に移住しようとしたときに妹は言った。「あなたはそこに自分をうずもれさせて、生きてる魂に話しかけるつもりはないのよ。ひきこもって、精神状態もわるくなっていくわ。そこで知っている限り全員の紹介状をあなたに書くわ。そのうちの何人かは、覚えてる限りではすごくいい人だったから」
紹介状をもらった女性、サップルトン夫人がいい人の部類にはいるのかどうかフラムトンはわからなかった。
「このあたりの人は、ほとんど知り合いですか?」姪は、無言での交流は十分と判断してそう尋ねた
「ほとんどだれも知りません。私の妹がここの牧師館に滞在したことがあって、そう4年ほども前になりますか、そして私にここにいる何人かの紹介状をくれたわけです」フラムトンは、発言の最後には少し後悔の念をただよわせ、そう答えた。
「じゃあ私のおばについては、全く何もしらないわけね」落ち着いた少女はそう続けた。
「名前と住んでいるところだけです」その訪問者は、サップルトン夫人が結婚しているか、未亡人なのか戸惑いながら、そう認めた。なんともいえない部屋の感じからは、どことなく男性が住んでる感じがしたが。
「おばの悲劇はちょうど3年前に起こったの」その子供は続けた。「あなたの妹さんがいた後ってことね」
「悲劇?」フラムトンは、この静穏な田舎に悲劇とはまた場違いな、と思いながらそうたずねた。
「10月の夕方にしては、窓を大きく開けてると思いません?」姪は、庭に向かって開いている大きなフランス風の窓を指差した。
「この時期にしては暖かいですからね」フラムトンは答えた。「あの窓が悲劇となにか関係あるんですか?」
「ちょうど三年前の今日のことです。あの窓から、おばの主人と二人の弟たちは狩猟で出かけていったんです。ところが帰ってきませんでした。自分たちの好みの狩猟場に行こうと、原野を横切っているときに、三人とも不安定な沼地に囲まれてしまったのです。そう、ひどく雨の多い夏でしたから例年なら大丈夫な場所でも、とつぜんなんの前触れもなしに沈み込んでいきました。死体も見つかりません。痛ましい話です」子供の声からはおちついた感じがなくなって、とつとつとした話ぶりだった。「おばはかわいそうに、いつか三人と、いっしょにいなくなった小さな茶色の犬が帰ってきて、いつもそうしていたように、あの窓から入ってくると思ってるんです。だからすっかり暗くなるまで、あの窓は夕方はいつもあけっぱなしになっています。かわいそうなおば。よくどうやって家からでていったかを話してくれました。叔父は白のレインコートをうでにかけていたと。ロニーは末の弟ですが、『バーティ、なぜ飛び跳ねてるの?』なんて歌いながら、彼女がそうされると気に触ると言っていたので、いつもそうやって彼女をからかっていたのです。今日みたいな静かな落ち着いた夕暮れには、窓からみんなが歩いて入ってきそうな気がしてぞっとします、わかります?」
姪が少し身震いして話をとめたので、おばが遅れたことを謝ろうと大騒ぎをしながら部屋にはいってきた時、フラムトンはほっとした。
「ベラがちゃんと楽しませてくれてたといいんだけど」とおばが言ったので、
「とても興味深かったですよ」フラムトンは答えた。
「窓が開いてるのは気になさらないでください」サップルトン夫人は手短にいった。「わたくしの主人と兄弟が狩りから帰ってきて、直接そこから入ってきますので。今日は沼地のほうに狩りにいってるから、わたくしのカーペットはざんざんなことになりそうだわ。あなたがた男ってそうよね?」
彼女は、狩りや鳥が少ないこと、この冬のカモの見込みについて楽しそうにおしゃべりした。フラムトンにとっては、ただただ恐ろしかった。必死に努力してなんとか、話を幽霊とは関係ないことにもっていくことにも少しは成功した。ただ彼女が気もそぞろで、その目はたえず自分の後ろの開いた窓、その向こうの庭に向けられていることにも気づいていた。まさしくこの悲劇の日に訪問してしまったことは、不幸な偶然の一致としかいいようがなかった。
「医者たちは口をそろえて、私が完全な休養を取るようにと、精神的に興奮しちゃだめだと、激しい運動のようなことも避けてくださいといいました」フラムトンはそう知らせると、どうしようもないほど誤解がひろがって、全く知らない人や偶然知り合った人が自分の病気や症状、原因や治療法についてどんなことでも聞きたがるとこぼした。「食事についても、医者たちはあまり意見が一致していないくらいですから」
「そうなの?」サップルトン夫人は最後にはあくびをかみころしたような声で答えた。それから急にはっとして注意をむけた、とはいってもフラムトンの言っていることにではなかった。
「とうとう帰ってきた」彼女は叫んだ。「ちょうどお茶の時間だわ、かれらったら全身泥だらけみたいね?」
フラムトンはかすかにふるえて、姪のほうを分かってくれるよなという風に見た。少女は目に恐怖の色をうかべ、開いた窓から外を見つめていた。なんともいえないぞっとする恐怖のショックで、フラムトンは座ったまま振り返って、同じ方向を見た。
夕闇が濃くなる中に、3つの姿が庭を窓の方に向かって歩いてきている。全員両脇に銃をもち、その上一人は両肩に白いコートをはおっていた。疲れ果てた茶色の犬が彼らの後に続いていた。音も立てずに家に近づき、それから夕暮れに若い男のしゃがれ声が響きわたった「言ったろ、バーティ、なぜ飛び跳ねてるの?」
フラムトンは手当たりしだいにステッキとぼうしをひっつかむと、玄関、砂利道、門のどこがどこだかわからないくらい大急ぎで逃げ出した。そこに一台の自転車が道をやってきたが、出会いがしらにぶつかるのを避けるため生垣につっこむありさまだった。
「かえってきたよ、おまえ」白いレインコートをかかえた男は、窓から入ってきながらそういった。「かなりどろだらけになったけど、ほとんどは乾いたな。帰ってきたときに誰かが飛び出してったみたいだが?」
「ナッテルっていうのは本当にむちゃくちゃな人ね」サップルトン夫人は答えた。「自分の病気のことだけを話したかと思えば、あなたがたが帰ってきたら、一言のさよならも断りもなく走っていなくなったの。幽霊でもみたのかと思うわ」
「犬だと思う」姪は落ち着いて言った。「犬が怖いんだって言ってたもの。ガンジスの土手かどこかの墓地でバリア犬の一群に追いかけられたって。そして新しく掘った墓穴で、自分の上を犬たちがうなり声をあげたり、歯をむき出したり、口から泡をふいたりする中で一晩をすごしたんだって。神経をやられるのも無理ないわ」
とつぜんに荒唐無稽な話をでっちあげるのが、姪の得意技だった。
これくらいの機転は人生きかせたいものだね、彼女は15歳だけどね(かなり抜かりがないよね)